 |
人事労務相談顧問
|

経営にとって、従業員を雇用している限り、ヒトに関する課題・問題はなくなりません。
また、人事労務に関する法改正が頻繁に行なわれており、その都度、企業には対応が求められます。
人事労務管理に関する適切な対応をし、未然にトラブルを防ぐ上でも、人事労務に広く精通し、高い専門知識を持つ、ロジック社会保険労務士法人にぜひご相談ください。
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
10:00〜17:00
- 従業員を新たに雇用する場合の注意点は?
- 従業員から育児休業を取りたいという希望が出てきたけれども?
- 初めて定年になる従業員が発生するのだけれども?
- 職場で問題行動を頻繁に起こす従業員の対応は?
働き方や就社に対する価値観の変化

経済のグローバル化や不確実性の高い経営環境において、企業も従業員も生涯ひとつの会社に勤めることが既に常識ではなくなっています。
人材の流動化も進み、キャリアアップの重要な要素として、転職が定着しつつあります。 そのため、即戦力となり得る中途採用強化している中小企業も増えています。
人材の入れ替わりが激しくなる一方で、入社や退職における社会保険の手続きが頻発します。優秀な人材の確保において、社会保険事務手続きの効率化は避けては通れない課題といえます。
また、育児休業への考え方も変わってきています。
従来、育児休業を取得するのは、女性従業員が中心でしたが、働き盛りの男性従業員も取得する機会が増えています。
仕事と家庭を両立させるワーク・ライフ・バランスは日本政府が推奨する働き方改革の一環でもあるため、今後、育児休業の取得を希望する従業員が増えると考えられます。
ココがポイント!
育児休業を希望する従業員に対して、
育児休暇を取得させることは事業主の義務です。
育児休暇を取得させることは事業主の義務です。

よくある人事労務相談とは?

人事労務の問題は組織が大きくなると必然的に増えてしまいます。
歴史の長い中小企業では熟練工の定年退職も増え、新たな人材の獲得も必要です。 また、女性活躍社会が推進されている中で、育児休業に柔軟に対応する企業は社員の定着にもつながります。
新たなに従業員を雇用したい
少子高齢化の影響により、中小企業を中心に人手不足が深刻化しています。若手人材の確保が困難となっている中、高齢者や女性を従業員として迎える企業が増えています。
しかし、現在では65歳以上の労働者の雇用保険の適用や、パート・アルバイトの社会保険(健康保険や厚生年金保険)への加入対象が拡大しています。
ココがポイント!
従業員数500人以下の会社で働く人は、労使合意により社会保険への加入が可能になります!
- 1週間あたり決まった労働時間が20時間以上であること
- 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間見込みが1年以上であること
- 従業員数501人以上の企業、または従業員数500人以下で労使合意がなされていること
新たな従業員として短期労働者や65歳以上の労働者を雇用する場合は社会保険労務士に相談しましょう。

入社手続き(社会保険)について
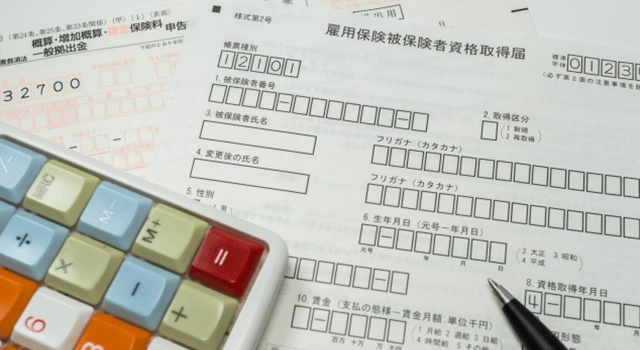
従業員が入社する度に発生する社会保険の手続きは、人事労務担当者にとって、大事な業務のひとつです。 一方で、社会保険手続きは入社がある度に対応します。
年末調整や基礎算定月などの繁忙期にも対応する必要があるため、入社するタイミングが分かったら、早めに準備しておきましょう。
入社手続きにおける主な社会保険事務作業は以下となります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格取得届
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
10:00〜17:00
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届について
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは、従業員を採用した場合に新たに健康保険、厚生年金保険に加入すべき人が生じた場合、事実発生から5日以内に事業主が提出する書類です。健康保険や厚生年金は会社(事業所)単位での適用となり、国籍・性別・賃金額に関係なく、その事業所に常時使用される人すべてが被保険者となります。
ココがポイント!
原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入
| 提出時期 | 事実発生から5日以内 |
| 提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参(CDまたはDVDなどの電子媒体も可) |
【参考】就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き│日本年金機構
【参考】健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届│e-Gov 電子政府の窓口-->
雇用保険被保険者資格取得届について
雇用保険被保険者資格取得届とは、雇用保険の適用対象となる従業員を初めて雇用する際に保険関係成立に関する手続き後に事業所を管轄するハローワークに提出する書類です。従業員が離職した場合も雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出しなければなりません。
雇用保険の適用範囲が拡大されました!
31日以上の雇用見込みがあること 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険被保険者資格取得届を提出する際は、添付書類も必要です。
- 労働者名簿
- 前職の雇用保険(失業保険)被保険者証
- 入社時のタイムカードまたは出勤簿(コピー可)
- 【パートタイム】雇用契約書または雇入通知書
- 【派遣労働者】派遣元管理台帳または派遣契約書
【参考】事業主の行う雇用保険の手続き│厚生労働省
【参考】雇用保険の適用範囲が拡大されました!│厚生労働省
健康保険被扶養者異動届について
家族を被扶養者にするときや、入社後に被扶養者となっている家族に異動があったときは健康保険被扶養者異動届の提出が必要です。健康保険被扶養者異動届は被扶養者の追加・削除、氏名変更があった場合、その事実が発生してから5日以内に事業主が提出します。
ココがポイント!
被扶養者のマイナンバーが必要です。お忘れなく
【参考】家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき│日本年金機構
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
10:00〜17:00
育児休暇の希望への対応について
近年では、女性だけでなく、男性の育児休業を希望する人が増えています。また、満1歳(一定の要件を満たせば、1歳6ヶ月)に満たない子供をもつ従業員が育児休業の希望を申し出た場合、事業者は育児休暇を与えなければなりません。
ココがポイント!
パートタイマーなどの有期雇用労働者も一定の条件を満たせば、育児休暇を付与しなければなりません
女性の場合、「出産後に8週間の産休を取得した後、産休明けから子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」の産後休暇を含めた1年間を育児休業として取得できます。
男性の場合、基本的に1年間の育児休業の取得が可能です。 育児休業給付金の支給要件は社会保険労務士にお問い合わせください。
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
10:00〜17:00
定年退職を迎える従業員がいる
中小企業の製造業を中心に高い専門性や技術を持つ熟練工が定年を迎える機会が増えています。就業規則に退職金規定が記載されている場合、企業には退職金の支払い義務が発生します。
退職一時金制度を採用している場合、企業の支払い能力の有無に関わらず、一括での支払い義務が発生します。
また、定年退職に関連する法改正が施行されており、「65歳までの雇用確保義務」が段階的に引き上げられており、2025年4月1日には全企業は、「65歳までの雇用確保義務」が無化されます。
どうなる?70歳までの定年延長
70歳就業確保法案が可決され、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務に!
2021年4月から日本は定年70歳時代に突入するため、定年退職が近い従業員を雇用している企業は再雇用制度を含めた制度の見直しが必要です。
雇用保険育児休業給付金

育児休業給付金とは、従業員が育児休業を取得しやすくし、職場復帰の援助・促進を目的とした職業生活継続支援制度のひとつです。
満1歳未満の子どもを養育するための育児休業を取得した場合、休業開始日から起算して1か月ごとの期間で支給されます。
支給には「支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること」や「各支給単位期間において就労日数が10日(10日を超える場合、就業時間が80時間以下)以下であること」などの要件があります。
有期雇用者の場合、無期雇用者と受給要件が異なるため、注意が必要です。
ココがポイント!
男性従業員も育児休業給付金の対象です
また、育児休業を取得した際、パパ・ママ育休プラス制度の要件を満たすと、子どもが1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に最大1年まで育児休業給付金が支給されます。
| 提出者 | 原則として事業主 |
| 提出書類 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 |
| 添付書類 | 賃金台帳や出勤簿・タイムカードなど 母子健康手帳の市区町村の出生届にかかる頁(写) ※住民記載事項証明(写)も可 振込先金融機関の通帳の写し |
【参考】育児休業給付について│厚生労働省 大阪労働局
近年、増えている人事労務トラブル

働く人の労働に関する意識も変わってきており、人事労務関連のトラブルも変化しています。 近年、増加している人事労務トラブルを把握しておくことで、事前に対策を立てられます。
- 労働時間や休憩時間
- ハラスメントによる職場秩序・職場環境の乱れ
- メンタルヘルスに関する問題
- 解雇や退職、人事評価に関する問題
- 労働災害や労災保険に関する問題
それでは、解説していきます。
労働時間や休暇に関する相談
2020年4月より時間外労働時間の上限規制が中小企業にも適用されています。また、有給休暇5日取得義務も施行されており、企業の労務管理の徹底が必須です。有給休暇の取得は労働者の権利でもあることも理解しておかなければなりません。
当然、時間外労働の割増賃金の不払いは法令違反となります。 従業員の労働時間や有給取得状況の管理が必要です。
ハラスメントによる職場秩序・職場環境の乱れ
パワーハラスメント、セクシャルハラスメントのほか、最近ではマタニティハラスメントによる職場の秩序・環境の乱れが社会問題となっています。職場での嫌がらせは、周りの従業員の不安を助長させ、退職率の悪化や精神疾患をきたす従業員が増えるなど企業の生産性にも大きな影響を与えます。
このようなハラスメントを発生させる問題社員に対応するためにも、ハラスメント防止に関する規定を就業規則に記載しておきましょう。
メンタルヘルスに関する相談
働き方改革法案の施行により、企業は産業医・産業保健機能の強化に関する取り組みが義務化されています。
- 産業医の活動環境の整備
- 健康相談の体制整備
- 労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進
- 面接指導等
労働者の健康確保は、事業主にとって、避けては通れない対策です。人事労働トラブルに発展させないように、事前に社会保険労務士に相談しましょう。

解雇や退職、降格など人事評価に関する問題
従業員の解雇は労働基準法で厳しく規制されています。現行の法律では使用者側の都合による金銭解雇は行えませんので、注意しましょう。 また、問題社員に対する降格や従業員の意に沿わない配置転換も人事労務トラブルの原因となっています。
就業規則の見直しや従業員へのヒアリングを通じて、公平公正な人事評価制度が必要です。
労働災害や労災保険に関する問題
仕事中のケガや長時間労働・休日出勤の常態化による過労死、精神疾患は労災保険の対象となります。企業と労働者とのコミュニケーションがうまくいかない(言い分が違う)場合、従業員が労働基準監督署に相談しに行くことも珍しくありません。
労働災害や労災保険に関する人事労務トラブルは労働裁判にも発展する可能性があるため、労災や労災保険に関する問題が起きた場合は、社会保険労務士に相談しましょう。
| 項目 | 料金 |
| 人事労務に関する相談 | 相談11,000円(税込) / 月 |
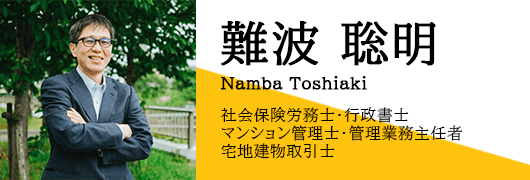
難波聡明 社会保険労務士の特徴
助成金代行申請実績年間200件以上
はじめまして。ロジック社会保険労務士法人、代表社員の難波聡明です。
「かつ丼みたいな会社づくりのお手伝い」で、経営理念−目標−会社の機能−組織−経営資源の方向性とバランスを整えます。
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
10:00〜17:00
ロジック社会保険労務士法人では、人事労務相談顧問としてご利用いただけます。 人事労務に関するご相談は、ロジック社会保険労務士法人にご相談ください。







